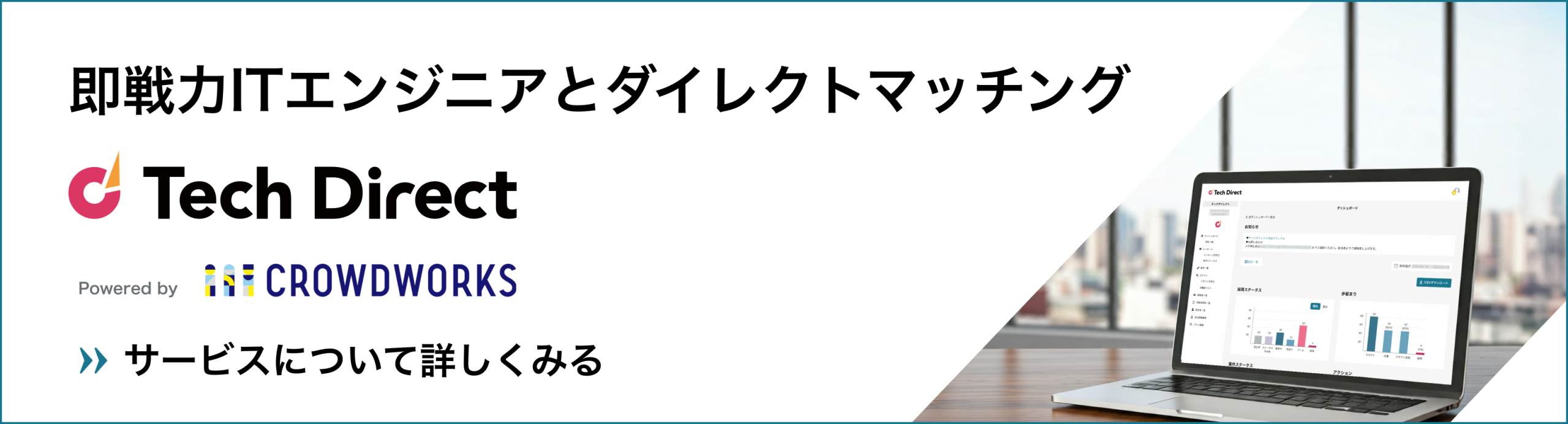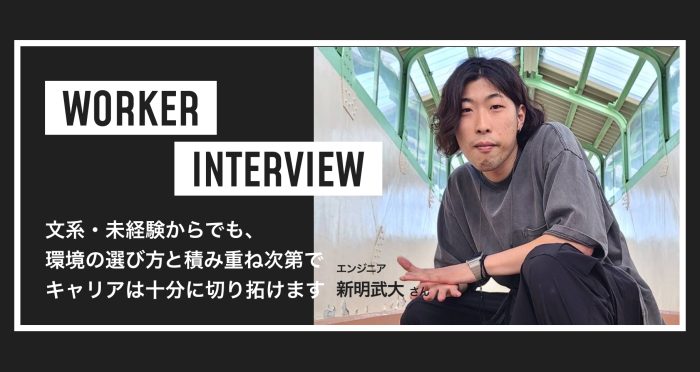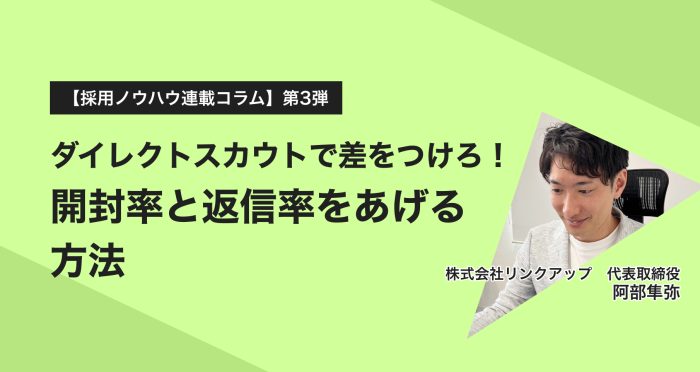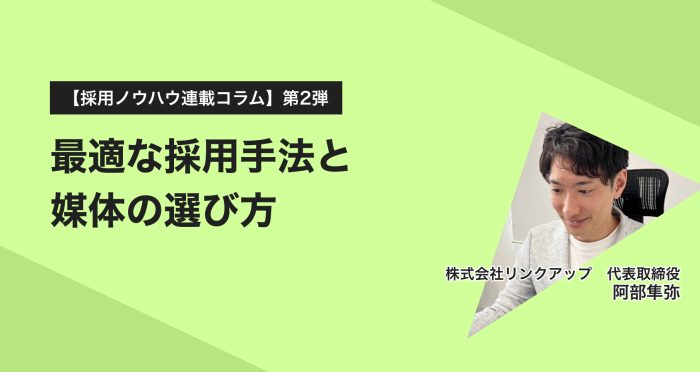2025.09.22
人材不足の中小企業必見!副業人材の探し方と契約の流れ
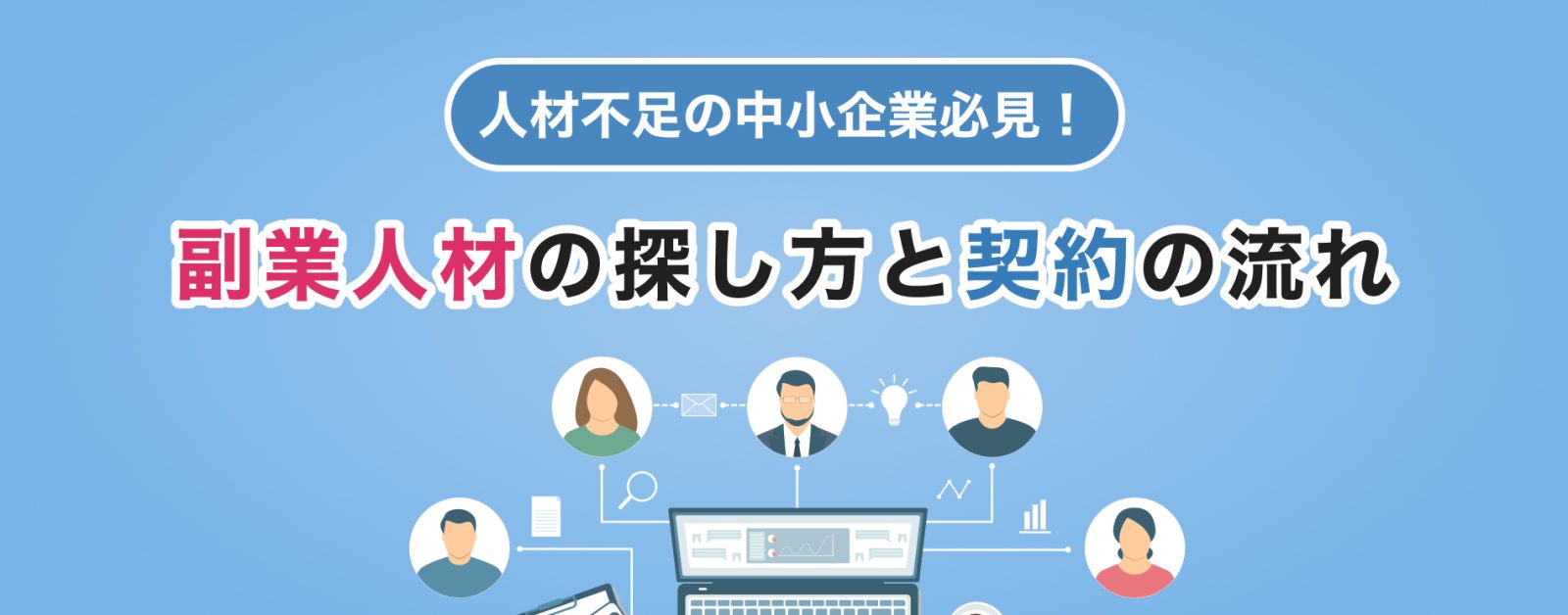
はじめに:なぜ今「副業人材」なのか?
少子高齢化や人口減少、業務の複雑化などにより、多くの中小企業が“人材不足”という課題に直面しています。
正社員を新たに採用するコストや時間がかかる中、「副業人材(兼業・フリーランスなど外部人材)」を活用するモデルが注目を集めています。専門性の補強、即戦力、柔軟な働き方の導入など多くのメリットがあり、反面、契約や運用での注意点もあります。
本記事では、副業人材の「メリットとリスク」「副業人材の探し方」「契約までの準備と流れ」を整理していきます。
1.副業人材とは何か/形態
まず、副業人材に関する基本的な定義と形態を理解しておくことが必要です。大きく分類して下記の2つの形態に分かれます。
- 副業・兼業人材
→正社員など本業を持ちながら、勤務時間外・休業日などを使って他社の業務を請け負う人材。大手企業の副業解禁などを通して、供給が増加。 - フリーランス/個人事業主
→所属する企業がなく、案件を請け負う人材。時間や業務形態の自由度が高い。
また、業務の種類としては、主に以下のようなタイプがあります。
タスク型:具体的な業務・納期・成果物が明確な仕事(例:記事作成、ロゴ・デザイン、ホームページ制作など)
プロジェクト型:中規模〜長期のゴールがあり、専門性が高い業務(例:新規事業立ち上げ、システム開発、マーケティング施策など)
ミッション型:期間・成果物に縛られず、中長期的に会社の戦略や改善に関わる役割を担う業務(経営戦略・経営企画など)
2.なぜ副業人材を使うのか:メリットとリスク
昨今注目されている副業人材ですが、多くのメリットがある反面、リスクや注意点も抱えています。ここでは実際に副業人材を採用することで得られる主なメリットと、その採用における注意点を整理していきましょう。
メリット
- 即戦力が得られる
→専門性の高いスキルを持つ人材を必要なタイミングだけ外部から確保できます。 - 成果や期間を限定して試せる
→ミスマッチによるリスクを抑え、まずは短期間や小さなプロジェクトから始めることができます。 - コストの効率化
→勤務時間外/稼働時間外での契約なので、正社員雇用よりもコストが抑えられる可能性(社会保険・福利厚生などの負担が減る)があります。 - 新しい視点・ノウハウの導入
→社外からの視点を取り入れることで、組織の活性化や業務改善、新規事業開発に繋がります。
リスク・注意点
- 契約上のトラブル(偽装請負など)
指揮命令関係・労働時間・報酬形態などが実質的に雇用関係とみなされるような場合、法的にリスクがあります。 - 秘密情報・知財の管理
社外人材に社内情報を扱わせる場合、個人情報の漏洩などを防ぐためにNDAなど契約での守秘義務の取り決めが必要となります。 - コミュニケーション・マネジメント
業務指示や進捗報告体制が曖昧だと齟齬が生じる恐れがある。副業人材は稼働時間も短いため、明確な指揮系統を確立する必要があります。 - 副業者自身の制約
本業の就業規則、副業の可否、勤務時間の制限など、副業者側の制約を事前に確認する必要があります。
3.副業人材の探し方
中小企業が実際に副業人材を探すためにはいくつかの方法があり、どのような人材を獲得したいのか、業務内容の特徴や予算に応じて方法を選定していく必要があります。
| 手段 | 特長 | 注意点 |
| スカウトマッチングサービス | 専門性の高い人材が登録しており、プロジェクト別、業務内容別に人材を探しやすい。 | 手数料や紹介料、マッチング精度や求めるスキルとの齟齬がないか確認が必要。 |
| クラウドソーシング・仕事媒介サイト | タスク型・小規模な案件に適する。発注までのコストが低い。 | クオリティのバラつきやコミュニケーションコストあり。納期遅れ等にも注意が必要。 |
| 人材紹介会社などのエージェント利用 | 専門性が高く、高めの報酬が必要な案件向け。信頼性のある人材を紹介してもらえることが多い。 | 紹介料やマージンが発生。契約後のサポート体制やフォローアップも確認が必要。 |
| リファラル採用 | 知人や取引先からの紹介で、信頼できる人材を得やすい。 | 公募とは異なり候補が限定される。期待値やスキルの幅の確認が難しいこともある。 |
| 地域支援機関・自治体の相談窓口 | 地方の場合、地方自治体や中小企業支援センターがプロ人材の紹介や補助制度を持っている場合がある。 | 手続きや紹介までの期間がかかることも。期待値を調整する必要あり。 |
4.契約前の準備と条件設定
人材候補が見えてきたら、契約に向けて以下の点を詰めておきます。
- 業務内容・成果物・ゴールの定義
何をいつまでにどのようなアウトプットで依頼するかを確認します。タスク型なら納期・量・品質、プロジェクト/ミッション型ならマイルストーンや成果指標を定めましょう。 - 報酬や支払条件
固定報酬か成果報酬か、時間単価かプロジェクト単位かを決めます。支払い時期や方法(銀行振込など)も明確にしましょう。経費負担(交通費など)があればどこまで負担するかなどの確認も必要です。 - 契約期間・見直し・終了条件
契約の始まりと終わり(期間限定か、延長可能か)、どのような条件で解約ができるか、どのような場合に見直すか、トラブルを防ぐためにも明示しましょう。 - 契約形態の種類
請負契約/準委任契約/委任契約のいずれかを確定します。指揮命令関係・成果責任の所在など法律上・税務上の区別を理解し、適切な形を選択する必要があります。 - 秘密保持・知的財産権
業務上知り得る情報の扱い(NDA)、成果物の知的財産の帰属、二次利用の可否など契約後のリスクにも気を配りましょう。 - 報告・コミュニケーション体制
進捗報告頻度、ミーティング、レビューの方法など管理体制も必要です。専任の担当者を置くなど、双方がコミュニケーションを取りやすい体制作りが重要です。
5.契約の流れ
契約前の準備が完了し、条件設定が完了したら、いよいよ人材候補との契約のフェーズです。下記のステップを確認しながら契約書の取り交わしまで完走していきましょう。
| ステップ | 主な内容 |
| ステップ 1:要件定義 | 社内で何を依頼するかを明文化し、契約可能な業務かどうか確認する(法務・経理・労務など) |
| ステップ 2:募集・候補者選定 | プラットフォームや紹介・公募等で候補者を募り、ポートフォリオ・実績・人となりを比較検討する |
| ステップ 3:見積もり・条件交渉 | 候補者から見積もりを取得、報酬・納期・業務内容など諸条件を詰める |
| ステップ 4:契約書作成 | 契約形態(請負/準委任等)、成果物・納期・報酬・秘密保持・知財などを盛り込んだ業務委託契約書を作成・双方合意する |
| ステップ 5:業務開始・管理体制の設定 | 担当者を決め、進捗確認・レビューの方法を取り決める。必要なら支援ツール導入をする(プロジェクト管理ツール等) |
| ステップ 6:報酬支払い・成果検収 | 納品物・成果の確認、報酬支払い。検収プロセスを明確にしておく |
| ステップ 7:振り返り・契約再検討 | プロジェクト終了後、成果・課題をレビューし、今後継続するか・改善すべき点を明らかにする |
まとめ
副業人材の活用は、中小企業が人材不足やコスト制約を乗り越える有力な手段です。ただし、「やってみるだけ」ではなく、準備・要件定義・契約形態・期待値調整・フォローアップなどを丁寧に行うことで、成功率が大きく変わります。
まずは小さな・明確な仕事から始め、自社にとっての“ベストな関わり方”を見つけていきましょう。
テックダイレクトを利用してみたい企業担当者様
お問い合わせはこちら