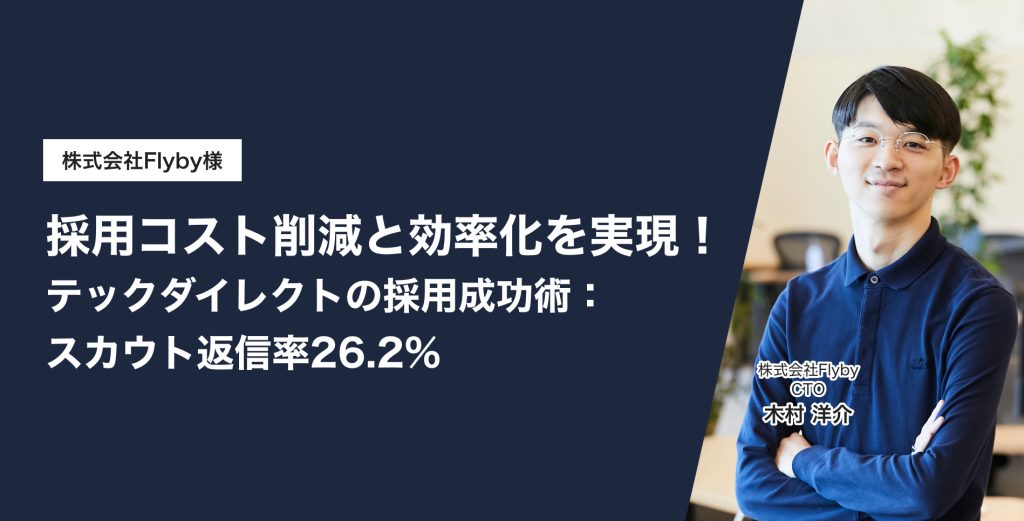株式会社Flyby CTO
慶應義塾大学理工学部 卒業。
新卒で株式会社野村総合研究所に入社。
国内大手の飲食・不動産・金融業界等、BtoBからBtoCまで幅広い業界に向けたプロジェクトに従事。テックリードとして、金融機関向け基幹システムや飲食店向け決済基盤等、大規模システム構築を推進。
2023年 10月 株式会社Flybyに参画。
多くのワーカーと直接面談できる魅力
テックダイレクトを利用したきっかけを教えてください
売上の増加に伴い、案件が増えたことでエンジニアが不足していました。
私たちのプロジェクトは通常、半年程度で完了することが多いため、採用に多額の費用がかかる方法では、プロジェクト終了後にその費用を回収できるか不確実で、リスクが大きくなってしまいます。
そんな中で、テックダイレクトは固定費用のみで追加費用が発生しない点が大きな魅力でした。リスクを抑えつつ、リーズナブルに利用できると判断し、導入を決めました。
テックダイレクトを使ってみて良かった点はなんですか?
一番高く評価している点は、マッチングから面談設定に進む割合が非常に高いことです。
多様な方と直接お話しできる機会が得られることは、私たちにとって大変ありがたく、非常に価値を感じています。
面談数が多く確保できている背景には、スカウトの返信率が高い(現在26.2%)という点が大きく寄与していると考えています。
採用できるという確信が事業拡大の後押しに
テックダイレクトを導入して解決したことはありますか?
新たな案件を受ける際の障壁が下がったと感じています。
スカウト返信率が高いため、一定期間内に何人の候補者と面談できるかを予測しやすくなり、面談数から採用人数を逆算できるようになったことが大きな助けとなっています。
また、ダッシュボードの存在も非常に重要なポイントです。
スカウト送信から採用に至るまでのプロセスをシステム上で一目で把握できるため、運用の効率化にもつながっています。
Flyby様が1か月という短期間で6名の採用を達成された背景には、どのような要因があったのでしょうか?
スカウトのプロセスをマニュアル化し、ルールベースで効率よく進めていることが大きな理由だと思います。
具体的には、基準をクリアした候補者にはスカウトを送り、面談数を増やすことで採用へと繋げています。このシンプルで効率的な流れが、短期間での成果に繋がっています。
スカウト対象者は、どのような基準で選定されているのでしょうか?
スカウト対象者は、言語やフレームワーク、そしてエンジニアとしての習得歴を掛け合わせた条件で選定しています。
月に何人面談するかという期待値に合わせて、各条件に合致する候補者数を逆算し、スカウトを送っています。
面談では主にスキルを中心に選考を行っており、スカウトの目的は、十分な候補者を確保し、採用に向けて見通しを立てることです。スカウトはあくまで面談の前段階として、候補者の数を増やし、効率的に進めるための手段となっています。
長期的に働ける職場環境がプロジェクトの円滑な進行を支える
週2日からの案件を掲載していると思うのですが、少ない稼働でもうまくワークしてもらえる秘訣はなんですか?
役割分担を明確にすることで、効率的な開発を実現しています。責務が明確に分けられていれば、たとえ稼働時間が80時間程度でも管理工数に大きな差は生じにくいと感じています。
開発で人を増やせるタイミングは限定されていると思っていて、適切なタイミングで人員を増やすことで、スムーズなプロジェクト進行を可能にしています。
Flyby様の案件の特徴を教えていただけますか?
弊社が最も得意としている分野は、ウェブアプリの開発です。特に2つのサービスラインを強みとしており、1つ目は、製造業などのお客様向けに提供する、複雑なロジックを要する基幹システムの開発です。これらは一般的に半年から1年程度の長期的なプロジェクトになります。
2つ目は、プロダクトをお持ちのお客様と二人三脚で進める、3カ月程度の短期間で機能追加を行っていくクイックな案件です。これらの案件は、年に何回も立ち上がることが多い点です。
Flyby様の案件の魅力はどんなところですか?
安定した案件獲得が強みで、長期的に継続して働ける環境を提供しています。多くの方が1年以上の長期にわたり活躍しています。
長期間ご一緒にお仕事をされている方々は、互いに顔なじみなことも多く、「以前この方と共に取り組んだ仕事があった」といった事例が自然に生まれます。
そのため、初めての相手と案件を進める際よりも、一緒にお仕事をした経験があるエンジニア同士で業務を行う方がスムーズに進むため、継続しやすいのではないかなと思います。
Flyby様の今後の展望を教えてください。
弊社は今後も、複雑性の高い業務システムやエンタープライズ領域に対して積極的にアプローチしていきます。これまでに培ってきた要件整理・上流設計の知見や、複雑な権限・データ構造への対応力を武器に、より本質的なシステム課題の解決に取り組んでまいります。
また、開発効率の継続的な向上を重視しており、今後はAIを活用した開発プロセスの最適化に全面的に舵を切る方針です。AIドリブンな設計・実装体制を構築することで、品質とスピードの両立を図ってまいります。
こうした体制を支える上でも、単なるコーディングスキルにとどまらず、業務理解や設計思考、知的好奇心を兼ね備えた次世代のエンジニアを積極的に採用・育成していきます。技術的な挑戦を楽しみながら、クライアント企業の本質的な価値向上に貢献できるチームづくりを目指していきます。